前回は改善して得られるものと新しいことを運用に取り入れた場合に発生する労力について考えてみました。今回は新しいことを「学習」することについて触れてみたいと思います。
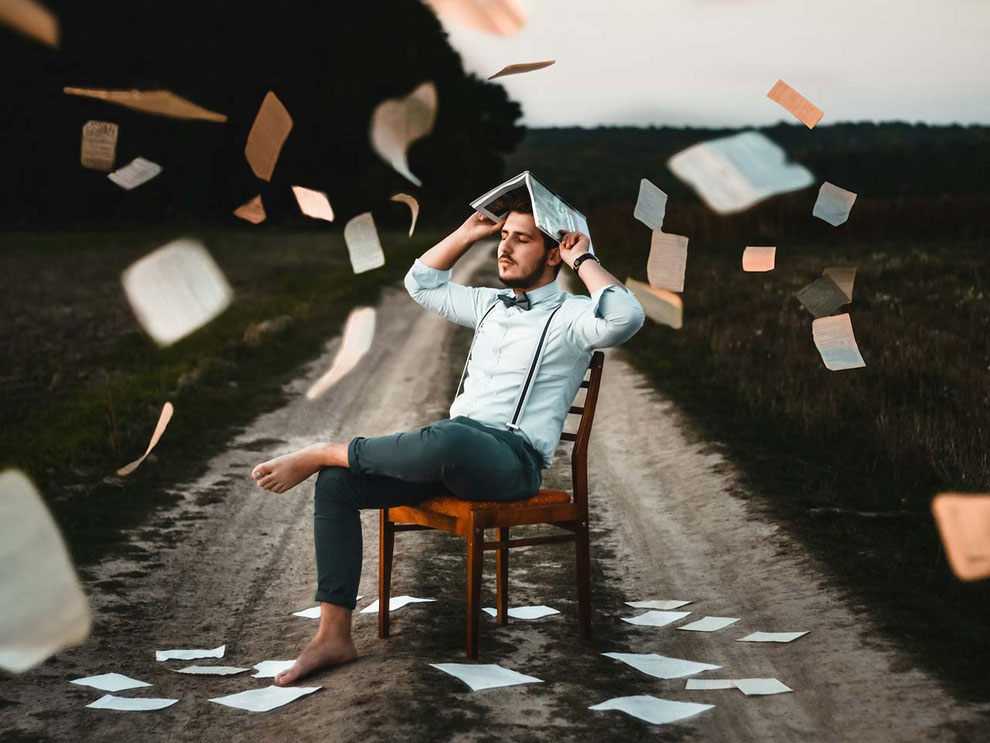
「新しいことを学習する」コスト
前回、あなたがある商店の店主として、制作会社から提案されたWebサイトに関する新しい施策を取り入れるかどうか検討する際に改善して得られるものと新しいことを取り入れる労力のバランスを考えた方が良いと申し上げました。今回はその「労力」の部分について少しつっこんで申し上げたいと思います。
こう言ったシチュエーションで「労力」と言った場合、思いつくのは担当者が新しくブログ記事を書いたりSNSで発信するための写真をとったり文章を作成する作業を行う、というイメージでしょうか。担当者にとっては他の業務との兼ね合いを考えて「やれそうかどうか」を判断する場面かと思います。この場合もう一つ考えていただきたいのは「新しいことを学習する労力」という大袈裟にいうと隠れた「コスト」です。
大抵の施策の訴求点としては「労力が低減できる」あるいは「小人数で今までできなかったような訴求ができる」その結果「効果を得つつコストの低減が見込める」というお話に結びつく展開がなされることが多いと思います。
その際に割合忘れられがちなのが「新しいことを学習する労力」なのではないかと思います。担当者は新しいブログシステムやSNSの利用にあたって、記事を作成する作業ができるようになる前に導入されたシステム等の使い方を学ばなければなりません。その労力というのが結構馬鹿にならないものだと思います。
もちろんこれは担当者のICTスキルによっても大きく変わってきます。慣れている人であれば時間も労力も最小限で済むかもしれませんがそうでない場合は時間も労力もかかります。
これはいうまでもなく「人件費」に直接関係してきます。あまりに負荷が大きいと会社全体としては効率が悪いという見方もできるでしょう。ただし長い目で見れば施策の効果で売り上げが上がり必ず回収できるという状況であればこれは問題ないかもしれません。
この点は個々の状況によりますのでどの程度の負荷とそれに伴う労力から発生する人件費については統一的な基準はありません。ただ、このような事柄を勘案した上で慎重に決めていく必要があると思います。
ICTやWebの学習コストについて
ここからは全くの私観になります。
ICTの活用やWebサイトの利用が私たちの生活に入ってきてからだいぶ時間が経ちました。この間PCやスマホのと言ったハードウェアの進歩とWebもふくめたサービスの進化は全く驚くべきもので、そしてそれらは今も止まることなく進んで行っています。一時代前から比べると格段の進歩と言えるでしょう。
しかし進歩を強く感じる一方、大きく変わらないのが「学習コスト」だと思います。新しい機器、新しいサービス、私たちがそれらを手にすると今までの知識や身につけた操作方法はご破産となり、新しいそれをふたたび「学習しなければならない」ということが繰り返されてきたと思います。いわば「賽の河原の石積み」といったら大袈裟かもしれませんが...
新しく得られるものの前にはそのような「学習コスト」は大した問題ではないという見方は承知の上で、個々の「学習コスト」の社会全体の総和を考えた時、「これは全体として本当に効率が良いと言えるのか?」という疑問は私の中では完全に打ち消すことができないのというのが正直な思いです。
ICTやWebが一部の人のものだった時代には問題なかったとしても、社会のユニバーサルサービスの一つとして皆が使用するものになってく方向にさらに進んでいくのであれば考えていく必要があると思います。UIやUXといった課題が出てきている今、強く感じるのです。
ただし、私自身も今の時点で正解はわかりません。自分のこととして言えば日々の業務に向き合っていく中でその課題を意識して自分なりに答えは探っていきたいと考えています。
次回に続きます。
